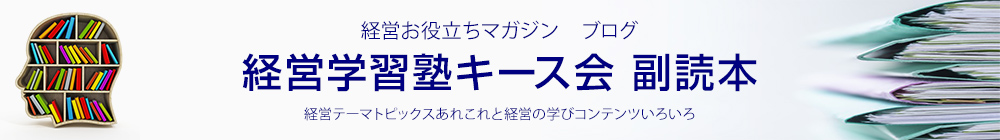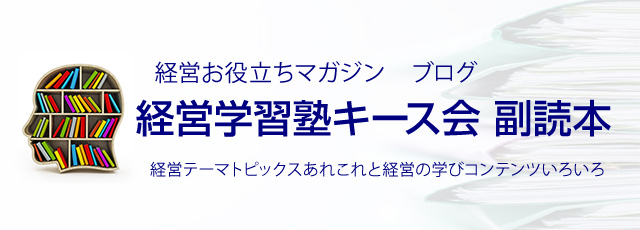事業承継スキーム(19) 生前贈与(1) ~連年贈与の一括贈与認定、名義預金
連年贈与の一括贈与認定、名義預金
今回から生前贈与のテーマに入ります。いわゆる相続対策の基本の王道です。法人ではなく個人間の資産やりとり、経営者個人としての方法論です。
簡単に言えば「ものをあげる、もらう」です。年間110万円までの基礎控除があり、それ以内であれば贈与税はかからないというやつです。今までの取り上げてきた相続対策スキームの中では一番簡便な方法論に思えます。たしかに方法自体は現金贈与が主になるので、資産が現金メインであれば一番世話がないかもしれません。専門家を介在させなくても自分たちだけでやれそうです。
が、実は税務の専門家でない金融マン、保険、銀行FPなどにとっては聞かれて戸惑う解釈の悩ましい問題でもあります。名義預金や連年贈与の一括贈与認定など、租税回避のための資金移転と解釈され、一見問題なさそうなのに否認されてしまうケースもあり、何をもって大丈夫と言えるのか、税法としての理解と民法としての成立要件の理解が必要です。
相続税対策の理想形はやはり、現金での連年贈与ということになろうかと思います。不動産や株式などの資産があっても、相続人たちにとって不動産や株式である必要がなく、現金化が可能であるなら、やはり現金化してしまいたいでしょう。そして基礎控除を適用し、数年にわたって現金で子や孫に贈与していくという形に持っていければ、多角的に見ても理想ではないかと思います。しかしこの一連の贈与を被相続人の死後、単年の現金贈与ではなく、一括した総額の贈与とされる心配があるということです。
また、連年贈与の際に子や孫名義の銀行口座に現金を振り込んだとしても、この時に子や孫が未成年、学生の場合、預金通帳や銀行印を親世代や被相続人自身が管理していたりすると、それは名義預金ということになります。
まずしばらくはこの2つの難関「連年贈与の一括贈与認定」と「名義預金」の問題について少し専門チックに掘り下げて考えてみたいと思います。
この2つの難点を回避するために、金融系営業マンが留意事項として提案する定番の項目があります。いくつか挙げてみると、
1、贈与契約書を作成しておく
2、単年分110万ではなく、120万にして10万円の10%、1万円を毎年贈与税として納税しておく
3、その贈与税は受贈者が申告する
4、通帳と印鑑の名義は受贈者名義にする
5、その通帳と印鑑の管理は受贈者が持っておく
6、贈与の振込の時期と金額は毎年変える
7、贈与する総額はあらかじめ決めない
8、受贈者は15歳以上の者にする
などがよく言われるところです。これだけ留意しておけば大丈夫かというと、必ずしもそうとは言い切れないところが難関たるゆえんです。
まずは「連年贈与」ですが、そもそも何がダメなのか?上記2のように毎年ちゃんと贈与税を納めていればまさか否認の対象になるとは思えませんが、根拠の論点が違うようです。この点についての根拠の記述は国税庁ホームページのQ&Aにあります。
Q、毎年10年間100万円ずつ贈与すれば贈与税はかかりませんか?
A、各年の贈与額が110万円以下なら各年に申告の必要はありません。ただし、毎年100万円ずつ10年間受け取ることが約束されていたならば、その時点で1000万円を受け取る「権利」を贈与されたものとして、約束した年にさかのぼり、その年に1000万円
から基礎控除後の金額に贈与税がかかります。
とあります。それゆえその対策として上記6や7など時期や金額を変える、総額を決めておかない、となるわけです。するとこの論点からすると、1の贈与契約書はまずいとなります。1の論点はむしろ、毎年分その都度別の契約書を作成し、別件贈与であることのアピールが目的になります。
6や7の「時期や金額を変える」や「総額を決めておかない」と言っても、あらかじめ総額を受け取る権利の約束を「していない」、ということは「どうやって立証するのか」が付きまといます。ですので証拠になる書面は残さない、となりますが、そもそも贈与は「諾成契約」と言って「物の引き渡し」などを要件としない「当事者同士の同意」で成立する、というのが「民法上の贈与」です。つまり「口約束」で成立するということです。「書面」は、現金贈与においては何らを立証する役割も、「立証しない」役割も果たしません。
じゃあどうしたらいいの、についてはもう少し後半にしまして、次に「名義預金」のほうを考えていきたいと思います。